涙そうそう及び葬送サービスに関する検索ができます
お支払いについて >>
<当サイトは総額表示です>
戒名・法名・法号授与後の法要・供養の目次

【平日/土日祝】9:00~17:00

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】
※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

戒名・法名・法号授与後の個人の法要・供養

お葬式・葬儀が終わった後、または戒名・法名・法号授与をしていただいた後にも故人の供養をしていかなければなりません。故人を偲ぶ心、故人がどのような方だったかを子孫に伝え、供養していく事を忘れないようにしましょう。
戒名・法名・法号授与後に必要な法要・供養
中陰法要(ちゅういんほうよう)・追悼法要(ついとうほうよう)
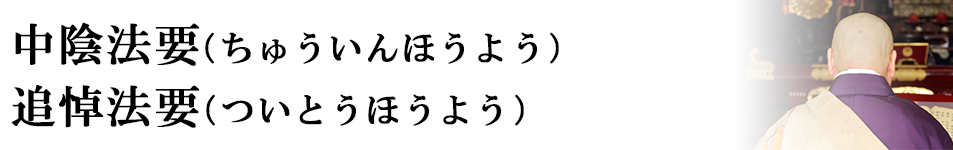
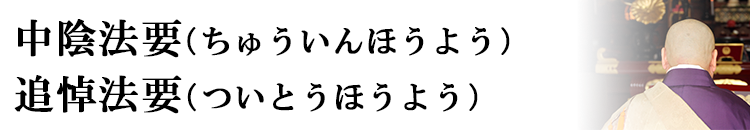
中陰法要とは故人が亡くなり、お葬式・葬儀の最後に行う初七日法要を始めとして、二七日法要・三七日法要・四七日法要・五七日法要・六七日法要・四十九日法要・百ヵ日法要まで故人を供養する法要を行うのが中陰法要(ちゅういんほうよう)・追悼法要(ついとうほうよう)となります。
宗派によっては四十九日法要を繰り上げて三十五日法要で終わらせる場合もありますが、一般的には四十九日法要まで行います。
仏教では個人が亡くなった後、輪廻転生するとされており転生する前に生前に行ったことを地獄にて裁判が七日ごとに行われ、その判決により来世が変わっていくと考えられております。
この七日ごとの裁判の無事を祈り生まれ変わった後が良くなるように願うのが中陰法要・追悼法要の起こりとなります。また、これは宗派全体の考えではなく宗派によっては別の解釈となります。
初七日法要
- お葬式・葬儀の告別式中、または火葬後に行う故人を供養する法要です。初願忌(しょがんき)とも呼ばれます。
二七日法要
- 遺族が亡くなってから14日目に行う故人を供養する法要です。以芳忌(いほうき)とも呼ばれます。
三七日法要
- 遺族が亡くなってから21日目に行う故人を供養する法要です。洒水忌(しゃすいき)とも呼ばれております。
四九日法要
- 遺族が亡くなってから28日目に行う故人を供養する法要です。阿形忌(あぎょうき)とも呼ばれております。
五七日法要・三十五日法要
- 遺族がなくなってから35日目に行う故人を供養する法要です。小練忌(しょうれんき)とも呼ばれております。
六七日法要
- 遺族が亡くなってから42日目に行う故人を供養する法要です。檀弘忌(だんこうき)とも呼ばれております。
四十九日法要
- 遺族が亡くなってから49日目に行う故人を供養する法要です。大練忌(だいれんき)・忌明け(きあけ)とも呼ばれております。
百ヵ日法要
- 遺族が亡くなってから100日目に行う故人を供養する法要です。卒哭忌(そっこくき)とも呼ばれております。
年忌法要・回忌法要
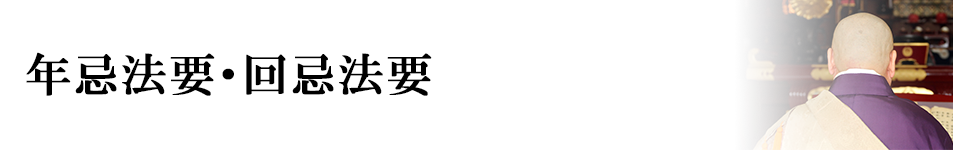
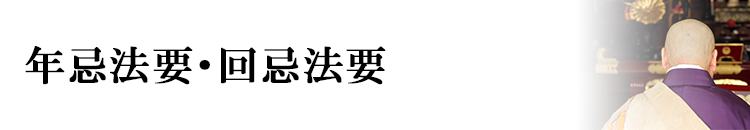
年忌法要・回忌法要とは、日本の仏教において定められた年の故人の祥月名日に追善供養をする事をいいます。年忌法要・回忌法要は区切りとして百回忌までしか書いておりませんが、五十回忌から50年ごとに百回忌・百五十回忌と続けて供養を行い続ける法要であります。
一周忌法要
- 故人が亡くなった翌年に行う法要で、この日までが喪中とされており、一周忌が終わるまでは喪に服して外出や旅行などは控えるのが一般的です。また、一周忌は故人が亡くなってから一周(一年経過)した日の事をいいます。
三回忌法要
- 故人が亡くなった年の翌々年に行う追善供養です。よく間違えられますが、一周忌が終わってから二年後に三回忌ではなく故人が亡くなった年を1年、翌年を2年、そして翌々年を三年と数えて三回忌となっております。
七回忌法要
- 故人が亡くなってから6年後に行う追善供養です。
十三回忌法要
- 故人が亡くなってから12年後に行う追善供養です。
十七回忌法要
- 故人が亡くなってから16年後に行う追善供養です。
二十三回忌法要
- 故人が亡くなってから22年後に行う追善供養です。
二十七回忌法要
- 故人が亡くなってから26年後に行う追善供養です。
三十三回忌法要
- 故人が亡くなってから32年後に行う追善供養です。三十三回忌は弔い上げと言われており、死者が仏から神様となり、ご先祖様の仲間入りをするとされております。
三十七回忌法要
- 故人が亡くなってから36年後に行う追善供養です。
四十三回忌法要
- 故人が亡くなってから42年後に行う追善供養です。
四十七回忌法要
- 故人が亡くなってから46年後に行う追善供養です。
五十回忌(遠忌)法要
- 故人が亡くなってから49年後に行う追善供養です。五十回忌を目途に以後50年ごとに年忌法要・回忌法要を行います。また五十回忌からは遠忌(おんき)と呼ばれ五十遠忌とも呼びます。
百回忌(遠忌)法要
- 故人が亡くなってから99年後に行う追善供養です。
年忌法要・回忌法要一覧表

| 周忌 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|
| 1周忌 | 2025年 | |
| 3回忌 | 2024年 | |
| 7回忌 | 令和2年 | 2020年 |
| 13回忌 | 平成26年 | 2014年 |
| 17回忌 | 平成22年 | 2010年 |
| 23回忌 | 平成16年 | 2004年 |
| 27回忌 | 平成12年 | 2000年 |
| 33回忌 | 平成6年 | 1994年 |
| 37回忌 | 平成2年 | 1990年 |
| 43回忌 | 昭和59年 | 1984年 |
| 47回忌 | 昭和55年 | 1980年 |
| 50回忌 | 昭和52年 | 1977年 |
| 100回忌 | 昭和2年 | 1927年 |
※平成31年は4/30までの元号となります。5/1からは新元号となります。
例①:一周忌 令和元年 2025年
今年に一周忌を行う方は、2025年亡くなった方です。
例②:十三回忌 平成26年 2014年
今年に十三回忌を行う方は、平成26年2014年に亡くなった方です。
故人の供養

魂抜き・魂入れ
お葬式・葬儀が終わってから四十九日法要までに告別式で使用した仮位牌から本位牌に入れ替えるのが一般的で、この時にお坊さんによる【魂入れ】と【魂抜き】の法要が必要になってきます。
【魂入れ】とは、仏像や位牌に魂を入れ、これから先祖を供養して祈る先をつくる儀式で、【魂抜き】は、その魂を抜いて浄土へ送る儀式の事です。仮位牌の魂を抜き、本位牌へ魂を移し故人の供養を行います。
また、お墓をお持ちの方はお墓の魂抜きを行い、戒名・法名・法号彫りを行ってもらい、お墓の魂入れを行いましょう。
戒名・法名・法号授与後に魂入れ・魂抜きが必要な物
■仮位牌・本位牌
■お墓
■お仏壇(お仏壇を新しくする時など)
■家(いままで住んでいた住居を取り壊す時など)
■井戸(いままで住んでいた住居を取り壊す時など)
納骨供養
納骨供養は故人のお骨をお寺の納骨堂、お墓、樹木へお骨を納める時に行う法要です。
部屋供養
故人が使われていたお部屋を清め、供養するための法要です。マンションなど一人でお住まいの方がお亡くなりになり、次の方が移り住む前に部屋供養を行う法要です。
水子供養
流産または人口妊娠中絶によりお亡くなりになった胎児に子供用戒名授与を行い供養する法要です。
故人の定期法要

祥月命日
故人がお亡くなりになった日を命日として、毎月の同じ日に故人の供養、先祖代々の供養を行います。一般的な檀信徒の方は月経(つきぎょう)と呼び毎月自宅のお仏壇の前でお坊さんに読経をしてもらいます。
お盆・初盆法要
7月・8月のお盆には先祖が自宅に還ってくるとされており、7月と8月のお盆期間(一般的には13日~15日)にお坊さんをお呼びして棚経を読経して供養してもらうのが習わしです。また、亡くなった方が初めてお盆を迎えるときは初盆(はつぼん)といいます。
法要・供養の費用
出張法要・出張供養

最も経済的な法事・法要となりますが、お客様にとっての負担が重くのしかかってきます。とは言っても、お仏壇での前の法事・法要が一般的のようです。
お寺法要・お寺供養

涙そうそう(終楽)への法事・法要依頼で最も人気なのが、お寺法事・法要です。その理由は、
☆最近のお寺さんは、椅子ありで正座の必要がほとんどない。
☆冷暖房・水洗トイレありで環境が整備されている。
☆関係者が、集まり易い場所を選べる。
☆料金(費用)が、リーズナブルである。
簡単で便利であり料金(費用)的に納得できるということで、お寺法事がお客様に受けているようです。
戒名・法名・法号授与の費用(料金)一覧表
涙そうそうでは一般戒名授与(信士・信女、釋・釋尼)から他の同業他社が対応していない子供用戒名授与・ペット戒名授与まで対応しており、非檀家のお客様の為にリーズナブルな値段設定をしております。
信頼と安心のお坊さんによる戒名・法名・法号授与の料金表をご覧ください。
戒名・法名・法号授与の費用(料金)一覧表(税込表記)


戒名・法名・法号授与のご案内
宗派指定には追加で5,500円が必要です
一般戒名授与(釋・釋尼)

一般戒名と呼ばれる位号の中では一番階位(ランク)の低いもので釋・釋尼は浄土真宗本願寺派・真宗大谷派にて授けられる法名です。
居士・大姉

信士・信女より位階(ランク)が上で、成人の男女で人格・徳に優れ、寺院もしくは社会に貢献された方に授けられる位号です。
院信士・院信

信士・信女に院号を足した戒名・法号であり、院号は寺院もしくは社会に大きく貢献された方に送る戒名・法号です。
院釋・院釋尼

釋・釋尼に院号を足した法名であり、寺院もしくは社会に大きく貢献された方に授けられる法名であります。
軒号

主に禅宗(臨済宗・曹洞宗)の信徒に授けられる号で、院号を授けられるほどではないが寺院や社会に貢献された方に贈られる称号です。
院日信士・院日信女

主に日蓮宗にて授けられる法号であり、院号と日号がついており寺院もしくは社会に大きく貢献した方に授けられる法号です。日号は日蓮上人の法を受け継ぐ意味を持っております。
院居士・院大姉

院号と居士・大姉号がついた戒名・法号であり寺院・社会に大きく貢献し信仰に厚く人徳に優れた方に贈られる称号であります。檀信徒でも総代を任せられる方によく贈られる称号です。
子供用戒名授与

未成年のうちに亡くなった子供に授けられる戒名で、成人未満17歳以下の方につけられます。
◯童子(どうじ)・童女(どうにょ)17歳までの子供に授ける戒名です。
◯孩子(がいし)・孩女(がいにょ)5歳までの子供に授ける戒名です。
◯嬰児(えいじ)・嬰女(えいにょ)3歳までの子供に授ける戒名です。
◯水子(みずこ)0歳の子供に授ける戒名です。
ペット戒名「天名」

《天名協会授与》ペットに授与される戒名です。

【平日/土日祝】9:00~17:00

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】
※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。

戒名・法名・法号授与後の法要・供養最新情報
- 戒名・法名・法号授与後の法要・供養最新情報
-
- グーグルで「初七日とは」と検索してみました。
- ◇第01位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第02位:葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識と ...
- ◇第03位:初七日法要の意味・行う時期・香典・お供え・お返しについて
- ◇第04位:初七日法要について - 意味や服装・お布施など | 「イオンのお葬式」コラム ...
- ◇第05位:初七日法要 ~儀式の意味や流れ~ | 葬儀 - 価格.com
- ◇第06位:初七日法要について - はじめてのお葬式ガイド | いい葬儀
- ◇第07位:初七日〜忌明法要 - 法事・法要 - 葬儀の知識|葬儀・葬式・家族葬なら ...
- ◇第08位:四十九日
- ◇第09位:初七日から始まる「忌日法要」の供養方法・心得とは | ギフト ...
- ◇第10位:葬儀と初七日を一緒に行う場合とは?香典やお布施についても解説 ...
- グーグルで「初七日 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識と ...
- ◇第02位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第03位:初七日法要 ~儀式の意味や流れ~ | 葬儀 - 価格.com
- ◇第04位:初七日法要の意味・行う時期・香典・お供え・お返しについて
- ◇第05位:初七日
- ◇第06位:初七日から始まる「忌日法要」の供養方法・心得とは | ギフト ...
- ◇第07位:四十九日
- ◇第08位:葬儀と初七日法要を同時にできる?一緒にする場合の時間や香典を解説 ...
- ◇第09位:初七日法要について - 意味や服装・お布施など | 「イオンのお葬式」コラム ...
- ◇第10位:初七日法要について - はじめてのお葬式ガイド | いい葬儀
- グーグルで「初七日 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第02位:初七日法要にお坊さんを手配【お坊さん便】
- ◇第03位:初七日で必要なお布施の相場とは | Shaddyのギフトマナー辞典
- ◇第04位:葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識と ...
- ◇第05位:初七日のお布施の金額相場をご紹介!お布施の渡し方についても解説 ...
- ◇第06位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第07位:葬式費用の範囲 ~控除対象になるもの・ならないもの~|相続税の申告 ...
- ◇第08位:千葉県内の葬儀葬式に各宗派のお坊さんを派遣・紹介
- ◇第09位:葬儀のお布施の相場は?渡し方は? | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第10位:神奈川県内の葬儀葬式に各宗派のお坊さんを紹介
- グーグルで「初七日 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識と ...
- ◇第02位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第03位:神奈川県内の葬儀葬式に各宗派のお坊さんを紹介
- ◇第04位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第05位:千葉県内の葬儀葬式に各宗派のお坊さんを派遣・紹介
- ◇第06位:四十九日法要のマナーと基礎知識
- ◇第07位:初七日法要のお布施の金額相場は?お布施の渡し方や包み方もご紹介 ...
- ◇第08位:初七日法要にお坊さんを手配【お坊さん便】
- ◇第09位:【まとめ表あり】葬式費用の範囲~相続税計算時に控除できるもの ...
- ◇第10位:二七日・三七日・四七日・五七日・六七日・七七日法要について
- グーグルで「初七日 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:神奈川県内の葬儀葬式に各宗派のお坊さんを紹介
- ◇第02位:葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識と ...
- ◇第03位:千葉県内の葬儀葬式に各宗派のお坊さんを派遣・紹介
- ◇第04位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第05位:ご葬儀について
- ◇第06位:四十九日法要のマナーと基礎知識
- ◇第07位:7.5万円:一日葬の出張葬儀僧侶派遣(お坊さん手配)!
- ◇第08位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第09位:涙そうそうの葬儀プランを行える全国の斎場をご案内しています!
- ◇第10位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- グーグルで「四十九日とは」と検索してみました。
- ◇第01位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第02位:四十九日法要までの流れと基礎知識|小さなお葬式のコラム
- ◇第03位:四十九日法要のマナーと基礎知識
- ◇第04位:四十九日について - 意味や数え方、服装など | 「イオンのお葬式」コラム ...
- ◇第05位:四十九日にお香典は必要?服装は喪服?知っていれば慌てない。四十九 ...
- ◇第06位:四十九日の意味とは? 四十九日までは中陰壇、その後は仏壇で供養
- ◇第07位:四十九日法要について - はじめてのお葬式ガイド | いい葬儀
- ◇第08位:仏教で四十九日の法要の意味とは?中陰壇のことまで詳しく解説!|終 ...
- ◇第09位:四十九日の法要に向けて、どんな準備が必要? | ギフトコンシェルジュ ...
- ◇第10位:四十九日までの過ごし方はどうする?忌中に避けるべきことも紹介|終活 ...
- グーグルで「四十九日 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:四十九日法要までの流れと基礎知識|小さなお葬式のコラム
- ◇第02位:四十九日で何を行う?法要の内容や目的を紹介 | お墓探しならライフドット
- ◇第03位:四十九日法要のマナーと基礎知識
- ◇第04位:四十九日の法要って何するの? [喪主ログ]
- ◇第05位:四十九日にお香典は必要?服装は喪服?知っていれば慌てない。四十九 ...
- ◇第06位:初七日・四十九日・忌日法要
- ◇第07位:四十九日法要の食事の内容は?費用相場や席順・挨拶も解説します ...
- ◇第08位:四十九日
- ◇第09位:49日法要、準備から当日の流れまでを解説 - 香典返し・法事・法要の ...
- ◇第10位:ペットにも四十九日法要がある?法要の内容や必要な準備をご紹介|終 ...
- グーグルで「四十九日 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:四十九日法要までの流れと基礎知識|小さなお葬式のコラム
- ◇第02位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第03位:四十九日法要について | お寺ネット
- ◇第04位:四十九日に間に合わない!位牌の用意を忘れていた場合の対処法
- ◇第05位:49日法要や法事に関して多い相談 | 本寿院の戒名と49日のページ
- ◇第06位:「白木位牌」から「本位牌」へ。いつまでに必要?どのようにして作る ...
- ◇第07位:お位牌と戒名の豆知識−滝田商店
- ◇第08位:直葬のとき位牌は必要?位牌の意味や戒名についても説明します|終活 ...
- ◇第09位:四十九日法要 | 戒名ドットコムの戒名情報
- ◇第10位:お布施の相場は? 戒名によって金額は違う? 渡し方やタイミングも紹介 ...
- グーグルで「四十九日 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第02位:法名軸|いい仏壇
- ◇第03位:四十九日法要のマナーと基礎知識
- ◇第04位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第05位:スペシャルオファ [全品ポイントアップ&クーポン!] 【位牌 名入れ 無料 ...
- ◇第06位:浄土真宗では位牌が必要ない? | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第07位:四十九日法要までに喪主は何を準備する?宗派別の準備も解説します ...
- ◇第08位:【過去帳の知識】お寺に記入してもらう際のお布施の費用相場など ...
- ◇第09位:国産位牌 会津塗り 千倉 (金粉仕上げ) 4.0寸 (位牌 文字 込み) 【5年保証 ...
- ◇第10位:お位牌と戒名の豆知識−滝田商店
- グーグルで「四十九日 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第02位:法要日の計算ができます
- ◇第03位:法名軸|いい仏壇
- ◇第04位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第05位:3万円~四十九日法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第06位:お位牌と戒名の豆知識−滝田商店
- ◇第07位:ご葬儀について
- ◇第08位:四十九日法要について | お寺ネット
- ◇第09位:戒名の値段とは?知っているようで案外知らない!戒名の秘密 - はじめて ...
- ◇第10位:四十九日法要までの流れと基礎知識|小さなお葬式のコラム
- グーグルで「一周忌とは」と検索してみました。
- ◇第01位:一周忌とは|意味とお供えやお布施、お香典などのマナー|小さなお ...
- ◇第02位:一周忌・三回忌・年忌法要
- ◇第03位:一周忌とは – お布施や香典相場、香典返し、当日の服装など | 霊園・墓地 ...
- ◇第04位:一周忌とは?服装・香典・お布施・挨拶に関する知識を解説!|終活 ...
- ◇第05位:一周忌とは?法要の流れとマナーまとめ
- ◇第06位:一周忌法要について - はじめてのお葬式ガイド | いい葬儀
- ◇第07位:一周忌に参列いただく範囲と喪主・参列者が準備すること
- ◇第08位:一周忌はどんな服装が好ましい?立場や規模で変わる服装のマナー ...
- ◇第09位:一周忌に渡す香典!相場やマナーはどうなっている?
- ◇第10位:一周忌とは?基本知識・必要な準備についてわかりやすく解説! | お墓 ...
- グーグルで「一周忌 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:一周忌に参列いただく範囲と喪主・参列者が準備すること
- ◇第02位:一周忌とは|意味とお供えやお布施、お香典などのマナー|小さなお ...
- ◇第03位:一周忌法要の準備と一般的な流れ | 葬儀ナビ
- ◇第04位:一周忌とは?法要の準備は大丈夫?香典やお布施の相場、服装の ...
- ◇第05位:家族葬の一周忌法要の内容とは?家族のみで行う一周忌のマナーを ...
- ◇第06位:一周忌法要は家族だけでも大丈夫。親戚を呼ぶ場合は?|ウィズハウス
- ◇第07位:(2ページ目)家族葬の一周忌法要の内容とは?家族のみで行う一周忌の ...
- ◇第08位:Hyogo教区新報, 98号 : (内容)阪神・淡路大震災一周忌総追悼法要
- ◇第09位:【知っておきたい】法事・法要の食事メニューの選び方【一周忌・四十九日 ...
- ◇第10位:法事:一周忌の流れ | 喪服・葬儀の役立つコラム
- グーグルで「一周忌 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第02位:一周忌法要、施主はどう挨拶すべきか | 岩崎石材オフィシャルブログ
- ◇第03位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第04位:戒名が院号クラスの1周忌法要なら「10万円」が目安 | PRESIDENT ...
- ◇第05位:戒名授与|法事・法要なら「てらくる」
- ◇第06位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第07位:お布施の相場は? 戒名によって金額は違う? 渡し方やタイミングも紹介 ...
- ◇第08位:一周忌法要の際に渡すお布施の相場は?宗派別の料金相場も解説し ...
- ◇第09位:法要案内状【四十九日・忌明け・一周忌】文例とポイント|即日印刷 ...
- ◇第10位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- グーグルで「一周忌 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第02位:新盆と一周忌を同日に行う場合の案内状
- ◇第03位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第04位:一周忌法要と納骨式と新盆の案内状
- ◇第05位:3万円~一周忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第06位:生前戒名のご相談|49日、1周忌、50日祭、納骨等の法事・法要の相談 ...
- ◇第07位:戒名|いい葬儀
- ◇第08位:戒名のランクについて解説!金額相場から宗派の違いまでご紹介!|終 ...
- ◇第09位:戒名彫刻|墓石、石材なら静岡県伊東市の【駿河石材】の戒名彫刻 ...
- ◇第10位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- グーグルで「一周忌 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第02位:一周忌の挨拶のしかた | 岩崎石材オフィシャルブログ
- ◇第03位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第04位:一周忌に参列いただく範囲と喪主・参列者が準備すること
- ◇第05位:一周忌の挨拶のタイミングと文例を紹介!喪主と参列者それぞれ解説 ...
- ◇第06位:併修法要の場合のご案内状につきまして
- ◇第07位:霊標追加彫り 法名碑追加彫り お墓 墓石 追加彫刻 追加彫り 霊標 墓誌 ...
- ◇第08位:新盆と一周忌を同日に行う場合の案内状
- ◇第09位:一周忌に渡す香典!相場やマナーはどうなっている?
- ◇第10位:JA香川県 JAのお墓お仏壇メンテナンス・リフォーム
- グーグルで「三回忌とは」と検索してみました。
- ◇第01位:一周忌・三回忌・年忌法要
- ◇第02位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第03位:初めての三回忌!三回忌の流れからマナーまでを徹底紹介|小さなお ...
- ◇第04位:三回忌とは?三回忌の香典・お布施・挨拶・服装について徹底解説!|終 ...
- ◇第05位:2年目なのになぜ三回忌? | 浄土宗【公式WEBサイト】
- ◇第06位:忌日・年忌法要計算|ご逝去日から忌日・法要の日程表作成
- ◇第07位:年回忌法要早見表|安心できる葬儀ガイド
- ◇第08位:参列前に知っておきたい、三回忌法要でのお香典の相場と包み方 ...
- ◇第09位:三回忌法要のお布施の金額とは? | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第10位:三回忌は死後何年目のことですか?|葬儀・お葬式、法事に関する「よく ...
- グーグルで「三回忌 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第02位:初めての三回忌!三回忌の流れからマナーまでを徹底紹介|小さなお ...
- ◇第03位:三回忌の意味は?法事の内容や命日からの数え方などとあわせて紹介 ...
- ◇第04位:七回忌とは|意味と準備の内容、出席マナーを解説|小さなお葬式の ...
- ◇第05位:三回忌法要の内容や流れについて | 中本葬祭
- ◇第06位:法事・法要の常識-法事を主催する方~仏事まめ百科|メモリアルアート ...
- ◇第07位:『2017初夏・祖母三回忌の京都旅(でも内容的には道内多し…)』北海道 ...
- ◇第08位:「直撃LIVE グッディ!」2019年7月17日(水)放送内容 | テレビ紹介情報 ...
- ◇第09位:故人を追善供養する仏教の法要。その内容と費用は? | ファイナンシャル ...
- ◇第10位:三回忌のお供えに。花であなたの想い伝えます。心を贈る花ギフト|お供え ...
- グーグルで「三回忌 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:三回忌(さんかいき)、七回忌(ななかいき)
- ◇第02位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第03位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第04位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- ◇第05位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第06位:お布施のお金は新札を使ってもいいの?お布施の金額や書き方もご紹介 ...
- ◇第07位:表書きの種類
- ◇第08位:仏事の知識
- ◇第09位:法事のお返し、引出物をお考えの方へ のしや品物のまとめ[引き物ドット ...
- ◇第10位:超詳しい卒塔婆のおはなし - 卒塔婆・角塔婆・墓標・経木塔婆通販 ...
- グーグルで「三回忌 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第02位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第03位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第04位:三回忌の香典はどうすべき?書き方のマナーをレクチャー!
- ◇第05位:三回忌法要と納骨の際の案内状
- ◇第06位:3万円~三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第07位:「法事・法要」に関する記事一覧|葬儀・葬式なら【よりそうのお葬式】
- ◇第08位:三回忌の案内状(次回以降家族のみで)
- ◇第09位:一心寺 おせがき
- ◇第10位:仏式の戒名・法名について/香典返し・法事のお返し・49日引き出物専門店 ...
- グーグルで「三回忌 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:三回忌法要と納骨の際の案内状
- ◇第02位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第03位:3万円~三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第04位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第05位:3万円~三十三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第06位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- ◇第07位:=三回忌法要3万円(お坊さん手配・派遣)の自宅法事、全宗派・全国対応!
- ◇第08位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第09位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第10位:お布施について
- グーグルで「七回忌とは」と検索してみました。
- ◇第01位:七回忌とは|意味と準備の内容、出席マナーを解説|小さなお葬式の ...
- ◇第02位:7回忌法要はいつ行えばいいの?香典やお布施などのマナーも解説 ...
- ◇第03位:三回忌(さんかいき)、七回忌(ななかいき)
- ◇第04位:七回忌は何年後になりますか?|メモリアルアートの大野屋
- ◇第05位:七回忌の数え方とお布施 | 大人のためのbetterlife マガジン『enpark』
- ◇第06位:七回忌法要の準備と基本的なマナーとは? | Shaddyのギフトマナー辞典
- ◇第07位:忌日・年忌法要計算|ご逝去日から忌日・法要の日程表作成
- ◇第08位:年回忌法要早見表|安心できる葬儀ガイド
- ◇第09位:年忌 - Wikipedia
- ◇第10位:一周忌・三回忌・年忌法要
- グーグルで「七回忌 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:七回忌とは|意味と準備の内容、出席マナーを解説|小さなお葬式の ...
- ◇第02位:法要の流れ(時間・日程表)
- ◇第03位:七回忌法要の準備と基本的なマナーとは? | Shaddyのギフトマナー辞典
- ◇第04位:法事・法要の常識-法事を主催する方~仏事まめ百科|メモリアルアート ...
- ◇第05位:回忌法要はどうして行うの?それぞれの法事の内容を徹底解説します ...
- ◇第06位:イヤホンガイド「十八世中村勘三郎七回忌追善公演」特別放送のお知らせ ...
- ◇第07位:7回忌法要での挨拶は何を言えばいいの?ポイントや例文を解説します ...
- ◇第08位:法事・法要の七回忌、十三回忌について | 海鮮・会席料理のきじま
- ◇第09位:17回忌法要の案内状はどう書くの?挨拶の例文や返信の仕方もご紹介 ...
- ◇第10位:七回忌特別番組 秘蔵映像が語る 中村勘三郎“芸の神髄”(ドキュメンタリー ...
- グーグルで「七回忌 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第02位:その袋で大丈夫?お布施袋に関するマナーまとめ
- ◇第03位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- ◇第04位:三回忌(さんかいき)、七回忌(ななかいき)
- ◇第05位:表書きの種類
- ◇第06位:法要・供養お申込み | 千葉の納骨堂・生前戒名 萬徳院 釈迦寺
- ◇第07位:法事・法要の常識-法事を主催する方~仏事まめ百科|メモリアルアート ...
- ◇第08位:法事で納める「お布施」の相場は?|その他用意する物の値段や香典 ...
- ◇第09位:超詳しい卒塔婆のおはなし - 卒塔婆・角塔婆・墓標・経木塔婆通販 ...
- ◇第10位:7回忌の法要をお寺さんで行いたいのですが費用は?(2008年01月07日 ...
- グーグルで「七回忌 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第02位:三回忌(さんかいき)、七回忌(ななかいき)
- ◇第03位:漢詩 2月17日 法名 綉月院慧覚浄洋禅尼 七回忌景又春巡 | | 曹洞宗 大 ...
- ◇第04位:法事・法要とは?法事の種類や基礎知識
- ◇第05位:「法事・法要」に関する記事一覧|葬儀・葬式なら【よりそうのお葬式】
- ◇第06位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第07位:一心寺 おせがき
- ◇第08位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第09位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第10位:3万円~七回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- グーグルで「七回忌 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第02位:3万円~七回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第03位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第04位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- ◇第05位:納骨式初盆を一緒に行う場合の案内状について
- ◇第06位:日蓮宗の戒名授与|お坊さん便
- ◇第07位:お布施について
- ◇第08位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第09位:教導院様定心感謝 聖地親苑荘厳・境内地蔵尊安座法要
- ◇第10位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- グーグルで「十三回忌とは」と検索してみました。
- ◇第01位:13回忌の意味とは?13回忌とは何か、解説いたします|終活ねっとのお ...
- ◇第02位:【法事のマナー】十三回忌に正しいお香典とお供え物 - はじめてのお葬式 ...
- ◇第03位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第04位:年忌 - Wikipedia
- ◇第05位:忌日・年忌法要計算|ご逝去日から忌日・法要の日程表作成
- ◇第06位:年回忌法要早見表|安心できる葬儀ガイド
- ◇第07位:法要・年忌法要・十三仏信仰
- ◇第08位:十三回忌法要とお返しマナー/香典返し・法事のお返し・49日引き出物専門 ...
- ◇第09位:一周忌・三回忌・年忌法要 - 法事・法要・四十九日がよくわかる
- ◇第10位:十三回忌 (双葉文庫)
- グーグルで「十三回忌 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:法要の流れ(時間・日程表)
- ◇第02位:13回忌の意味とは?13回忌とは何か、解説いたします|終活ねっとのお ...
- ◇第03位:七回忌とは|意味と準備の内容、出席マナーを解説|小さなお葬式の ...
- ◇第04位:13回忌とは?準備やお供え・服装などのマナーについても解説!|終活 ...
- ◇第05位:法事・法要の常識-法事を主催する方~仏事まめ百科|メモリアルアート ...
- ◇第06位:十三回忌法要とお返しマナー/香典返し・法事のお返し・49日引き出物専門 ...
- ◇第07位:法事・法要の七回忌、十三回忌について | 海鮮・会席料理のきじま
- ◇第08位:「直撃LIVE グッディ!」2019年7月17日(水)放送内容 | テレビ紹介情報 ...
- ◇第09位:永代供養墓 | 曹洞宗天童山大雄院 | 茨城県日立市
- ◇第10位:法要 | 京都 眼の観音様 ~柳谷観音 立願山楊谷寺~
- グーグルで「十三回忌 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第02位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第03位:弔い上げとはなんですか?弔い上げの意味 | 大人のためのbetterlife ...
- ◇第04位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- ◇第05位:【セール adidas スウェット】アディダス トップス adidas WIDGAWNAP ...
- ◇第06位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第07位:永代供養墓について | 佼成霊園
- ◇第08位:法要・供養お申込み | 千葉の納骨堂・生前戒名 萬徳院 釈迦寺
- ◇第09位:超詳しい卒塔婆のおはなし - 卒塔婆・角塔婆・墓標・経木塔婆通販 ...
- ◇第10位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- グーグルで「十三回忌 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第02位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第03位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第04位:13回忌法要の準備(法要案内文)
- ◇第05位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第06位:3万円~三十三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第07位:【セール adidas スウェット】アディダス トップス adidas WIDGAWNAP ...
- ◇第08位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第09位:「法事・法要」に関する記事一覧|葬儀・葬式なら【よりそうのお葬式】
- ◇第10位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- グーグルで「十三回忌 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:お坊様手配・葬儀法事読経はご相談ください。
- ◇第02位:3万円~三十三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第03位:13回忌法要の準備(法要案内文)
- ◇第04位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第05位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第06位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- ◇第07位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第08位:今さら聞けない葬儀で使う言葉 | 平安典礼
- ◇第09位:東日教上人四十三回忌法要を迎え 高橋俊隆
- ◇第10位:供養と仏事(没後の世界) [高野山真言宗 那須波切不動尊 金乗院]
- グーグルで「三十三回忌とは」と検索してみました。
- ◇第01位:三十三回忌
- ◇第02位:年忌 - Wikipedia
- ◇第03位:33回忌法要への香典の金額はいくら?香典の書き方や水引きも解説 ...
- ◇第04位:三十三回忌法要とお返しマナー/香典返し・法事のお返し・49日引き出物 ...
- ◇第05位:弔い上げとはなんですか?弔い上げの意味 | 大人のためのbetterlife ...
- ◇第06位:三十三回忌の参列者は?|メモリアルアートの大野屋
- ◇第07位:年回忌法要早見表|安心できる葬儀ガイド
- ◇第08位:石原裕次郎さん、三十三回忌法要で弔い上げ まき子夫人「やっとゆっくり ...
- ◇第09位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第10位:忌日・年忌法要計算|ご逝去日から忌日・法要の日程表作成
- グーグルで「三十三回忌 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:七回忌とは|意味と準備の内容、出席マナーを解説|小さなお葬式の ...
- ◇第02位:三十三回忌法要とお返しマナー/香典返し・法事のお返し・49日引き出物 ...
- ◇第03位:回忌法要はどうして行うの?それぞれの法事の内容を徹底解説します ...
- ◇第04位:法事・法要の常識-法事を主催する方~仏事まめ百科|メモリアルアート ...
- ◇第05位:石原裕次郎さん、三十三回忌法要で弔い上げ まき子夫人「やっとゆっくり ...
- ◇第06位:法要の流れ(時間・日程表)
- ◇第07位:敗戦三十三回忌―― 予科練の過去を歩く | 宮田 昇 |本 | 通販 | Amazon
- ◇第08位:三回忌って何?知っておくべき法要のマナーは?
- ◇第09位:永代供養墓 | 曹洞宗天童山大雄院 | 茨城県日立市
- ◇第10位:法事・法要とは?法事の種類や基礎知識
- グーグルで「三十三回忌 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第02位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第03位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- ◇第04位:弔い上げとはなんですか?弔い上げの意味 | 大人のためのbetterlife ...
- ◇第05位:永代供養墓について | 佼成霊園
- ◇第06位:法要・供養お申込み | 千葉の納骨堂・生前戒名 萬徳院 釈迦寺
- ◇第07位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第08位:法事のお返し、引出物をお考えの方へ のしや品物のまとめ[引き物ドット ...
- ◇第09位:【セール adidas スウェット】アディダス トップス adidas WIDGAWNAP ...
- ◇第10位:新宿の墓地・永代供養墓「結の会」 | 曹洞宗 萬亀山 東長寺
- グーグルで「三十三回忌 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第02位:3万円~三十三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第03位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第04位:併修法要の場合のご案内状につきまして
- ◇第05位:三回忌の香典はどうすべき?書き方のマナーをレクチャー!
- ◇第06位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第07位:【セール adidas スウェット】アディダス トップス adidas WIDGAWNAP ...
- ◇第08位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- ◇第09位:法要の仕方と作法|仏壇と仏壇店を探すなら“いい仏壇”
- ◇第10位:過去帳に関するQ&A | インテリア仏壇 ルミエール
- グーグルで「三十三回忌 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:3万円~三十三回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第02位:お布施について|メモリアルアートの大野屋
- ◇第03位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- ◇第04位:永代供養|千葉市の家族葬は区民葬祭【公式】にお任せください
- ◇第05位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第06位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第07位:永代供養・墓地分譲 | 千葉県鴨川市浜荻 光玉山多聞寺
- ◇第08位:過去帳の書き方 | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第09位:喪主は誰でもなれるの? 菩提寺以外で葬式はできる? 今さら聞けない ...
- ◇第10位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- グーグルで「五十回忌とは」と検索してみました。
- ◇第01位:五十回忌のマナーと引き出物/香典返し・法事のお返し・49日引き出物 ...
- ◇第02位:50回忌の香典の表書きはどう書く?金額相場やマナーについても解説 ...
- ◇第03位:【ご住職監修】50回忌とは?喪主の準備やお布施、挨拶と弔問客の香典 ...
- ◇第04位:五十回忌
- ◇第05位:五十回忌
- ◇第06位:一周忌と五十回忌のご仏前|メモリアルアートの大野屋
- ◇第07位:年忌 - Wikipedia
- ◇第08位:年回忌法要早見表|安心できる葬儀ガイド
- ◇第09位:五十回忌法要にお坊さんを手配【お坊さん便】
- ◇第10位:今年・来年は何回忌
- グーグルで「五十回忌 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:五十回忌
- ◇第02位:五十回忌のマナーと引き出物/香典返し・法事のお返し・49日引き出物 ...
- ◇第03位:五十回忌のお布施はいくら包む?金額相場やお布施の包み方をご解説 ...
- ◇第04位:新選組隊士及関係者尊霊 「百五十回忌総供養祭」開催 - 新選組の ...
- ◇第05位:動画情報 | 福岡県文化団体連合会
- ◇第06位:法事検索【コラム 法要・法事の違い】| だんべー.com
- ◇第07位:法要の流れ(時間・日程表)
- ◇第08位:ご法要料理 – 上畑温泉さわらび
- ◇第09位:慶事・法事|和酒と和談 かこみ料理 醍庵
- ◇第10位:五十回忌法要と金額について - 法事・法要まとめ
- グーグルで「五十回忌 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第02位:五十回忌
- ◇第03位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第04位:【セール adidas スウェット】アディダス トップス adidas WIDGAWNAP ...
- ◇第05位:五十回忌法要にお坊さんを手配【お坊さん便】
- ◇第06位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- ◇第07位:法事のお返し、引出物をお考えの方へ のしや品物のまとめ[引き物ドット ...
- ◇第08位:超詳しい卒塔婆のおはなし - 卒塔婆・角塔婆・墓標・経木塔婆通販 ...
- ◇第09位:法要・供養お申込み | 千葉の納骨堂・生前戒名 萬徳院 釈迦寺
- ◇第10位:3万円~五十回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- グーグルで「五十回忌 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:(葬儀)香典・供物と会葬御礼(法要)
- ◇第02位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第03位:3万円~五十回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第04位:五十回忌法要にお坊さんを手配【お坊さん便】
- ◇第05位:【セール adidas スウェット】アディダス トップス adidas WIDGAWNAP ...
- ◇第06位:天台宗 > 天台宗について > 葬儀と供養について
- ◇第07位:一周忌と五十回忌のご仏前|メモリアルアートの大野屋
- ◇第08位:【セール パンツ】R3560 パンツ 60sベイカーパンツ(パンツ)|RNA-N ...
- ◇第09位:法名碑がいっぱいになった時はどうする? | 佐藤石材工業ブログ
- ◇第10位:過去帳に関するQ&A | インテリア仏壇 ルミエール
- グーグルで「五十回忌 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:3万円~五十回忌法要の出張法要僧侶派遣(お坊さん手配)涙そうそう!
- ◇第02位:十三回忌以降の年忌法要と弔い上げ
- ◇第03位:戒名・法名・法号授与とその後の供養
- ◇第04位:五十回忌法要にお坊さんを手配【お坊さん便】
- ◇第05位:五十回忌法要と金額について - 法事・法要まとめ
- ◇第06位:五十回忌のマナーと引き出物/香典返し・法事のお返し・49日引き出物 ...
- ◇第07位:[報告] 安政南海地震・津波の犠牲者五十回忌法要
- ◇第08位:お布施の金額相場はいくら?宗派・年忌法要別にご紹介します|終活 ...
- ◇第09位:一周忌と五十回忌のご仏前|メモリアルアートの大野屋
- ◇第10位:年回法要はいつまで続けるか
- グーグルで「魂抜きとは」と検索してみました。
- ◇第01位:魂抜きとは(閉眼供養) – 仏壇・お墓・位牌・人形など | 仏壇・仏具のこと ...
- ◇第02位:魂抜きとはなんですか?魂抜きの意味 | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第03位:魂抜きの意味とは?魂抜きとは何か、解説いたします|終活ねっとのお ...
- ◇第04位:魂抜き・お性根抜きのお布施金額の相場:お坊さんにいくら渡せばよいか ...
- ◇第05位:【お気持ちっていくら?】お仏壇の引っ越し方法!魂抜きとお布施の相場 ...
- ◇第06位:御魂抜き・御霊抜きとは(意味・解説)|地域最安の不用品回収ならグッド ...
- ◇第07位:「お墓の魂抜きとはなんですか?必要なの?」 | お墓文字彫り専門店 (株 ...
- ◇第08位:位牌の処分~業者の費用を格安にする方法と、浄土真宗のルール ...
- ◇第09位:魂抜き(お性抜き)について教えてください。 | 大阪(牧野・交野)の欧風 ...
- ◇第10位:3万円!魂抜き・閉眼供養:僧侶派遣(お坊さん手配)なら涙そうそう
- グーグルで「魂抜きの内容」と検索してみました。
- ◇第01位:魂抜きとは(閉眼供養) – 仏壇・お墓・位牌・人形など | 仏壇・仏具のこと ...
- ◇第02位:お墓の魂抜き・閉眼供養について。意味・相場・手順を紹介!|終活 ...
- ◇第03位:3万円!魂抜き・閉眼供養:僧侶派遣(お坊さん手配)なら涙そうそう
- ◇第04位:お墓じまい(魂抜き供養、お墓処分、ご遺骨整理・処分)案内!
- ◇第05位:2万円~お仏壇じまい・処分-魂抜き3万円、2,500円位牌処分 - 涙そうそうは
- ◇第06位:墓じまいを業者に依頼するとどうなる?依頼内容や金額について|お墓の ...
- ◇第07位:位牌の処分~業者の費用を格安にする方法と、浄土真宗のルール ...
- ◇第08位:解体工事のお祓い、地鎮祭、魂抜きは必要? - 解体工事の情報館
- ◇第09位:2平米16.8万円~お墓じまいの費用・料金のご案内
- ◇第10位:解体前の「玄がく斎」(居町)でお魂抜きがあり参拝 : 小林玲子の善光寺 ...
- グーグルで「魂抜き 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第02位:【解説】墓石に戒名彫刻するための値段相場は?石材店はどう選ぶ ...
- ◇第03位:魂抜きとは(閉眼供養) – 仏壇・お墓・位牌・人形など | 仏壇・仏具のこと ...
- ◇第04位:4万円「白木位牌魂抜き+本位牌魂入れ」セットの割引料金!
- ◇第05位:夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること|葬儀 ...
- ◇第06位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第07位:位牌の魂入れについて / 位牌の知恵ブログ
- ◇第08位:位牌の魂入れ(性根入れ)のお布施相場をお寺に聞いてみました
- ◇第09位:「お墓の魂抜きとはなんですか?必要なの?」 | お墓文字彫り専門店 (株 ...
- ◇第10位:墓誌の意味とは – 戒名彫刻、その費用(墓誌の価格、名入れ、追加彫刻 ...
- グーグルで「魂抜き 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第02位:Q & A|浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺
- ◇第03位:浄土真宗に位牌は必要ない?|浄土真宗の位牌の考え方
- ◇第04位:魂抜きとは(閉眼供養) – 仏壇・お墓・位牌・人形など | 仏壇・仏具のこと ...
- ◇第05位:夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること|葬儀 ...
- ◇第06位:墓誌の意味とは – 戒名彫刻、その費用(墓誌の価格、名入れ、追加彫刻 ...
- ◇第07位:戒名と法名と院号はどう違うの? | 永代供養・納骨の浄土真宗光乗寺
- ◇第08位:墓石への彫刻の値段はいくらくらい?詳しい相場をお教えいたします|終 ...
- ◇第09位:位牌の魂入れ(性根入れ)のお布施相場をお寺に聞いてみました
- ◇第10位:【解説】墓石に戒名彫刻するための値段相場は?石材店はどう選ぶ ...
- グーグルで「魂抜き 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第02位:位牌の処分について | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第03位:4万円「白木位牌魂抜き+本位牌魂入れ」セットの割引料金!
- ◇第04位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第05位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第06位:広昌山 観 音 寺|日蓮宗 寺院ページ
- ◇第07位:仏壇じまいは、魂抜き・仏壇処分・位牌などのお焚き上げ供養
- ◇第08位:【解説】墓石に戒名彫刻するための値段相場は?石材店はどう選ぶ ...
- ◇第09位:お墓開き・入仏式・開眼供養・魂入れとは?
- ◇第10位:浄土真宗 大谷派の仏像・位牌・仏壇について
- グーグルで「魂入れとは」と検索してみました。
- ◇第01位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第02位:仏壇の魂入れとは?|お布施・金額相場・準備・流れ・服装|終活ねっと
- ◇第03位:仏壇を買った後は開眼供養が必要!|開眼供養の準備と流れ
- ◇第04位:お墓の「魂入れ」って何?|開眼供養・お供え物・お布施・マナー|終活 ...
- ◇第05位:開眼供養・開眼法要とは – 日程と当日の流れ/お墓・仏壇・魂入れ・納骨 ...
- ◇第06位:名言、故事成語に学ぶ人材マネジメントの本質 - 第5回「仏作って魂入れ ...
- ◇第07位:仏壇を購入したい!購入するべき時期、購入のポイントについて解説 | お ...
- ◇第08位:【お気持ちっていくら?】お仏壇の引っ越し方法!魂抜きとお布施の相場 ...
- ◇第09位:「仏作って魂入れず」の英語・英語例文・英語表現 - Weblio和英辞書
- ◇第10位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- グーグルで「魂入れ 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:お墓の「魂入れ」って何?|開眼供養・お供え物・お布施・マナー|終活 ...
- ◇第02位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第03位:仏作って魂入れず - Magic Hour Blog
- ◇第04位:「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」放送内容 TBSテレビ:世界 ...
- ◇第05位:トルコ、中期経済計画は「仏作って魂入れず」か? | 第一生命経済研究所 ...
- ◇第06位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第07位:開眼供養・開眼法要とは – 日程と当日の流れ/お墓・仏壇・魂入れ・納骨 ...
- ◇第08位:「白木位牌」から「本位牌」へ。いつまでに必要?どのようにして作る ...
- ◇第09位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第10位:GHQでなく日本人が魂入れた憲法25条・生存権 (2ページ目):日経 ...
- グーグルで「魂入れ 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第02位:「白木位牌」から「本位牌」へ。いつまでに必要?どのようにして作る ...
- ◇第03位:墓誌の意味とは – 戒名彫刻、その費用(墓誌の価格、名入れ、追加彫刻 ...
- ◇第04位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第05位:位牌の魂入れなどの情報についてまとめてみました|終活ねっと
- ◇第06位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第07位:位牌の魂入れ(性根入れ)のお布施相場をお寺に聞いてみました
- ◇第08位:開眼供養・開眼法要とは?行う時期・服装・必要な費用など
- ◇第09位:位牌の安置場所・位牌の魂入れ
- ◇第10位:夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること|葬儀 ...
- グーグルで「魂入れ 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:Q & A|浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺
- ◇第02位:浄土真宗に位牌は必要ない?|浄土真宗の位牌の考え方
- ◇第03位:墓誌の意味とは – 戒名彫刻、その費用(墓誌の価格、名入れ、追加彫刻 ...
- ◇第04位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第05位:夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること|葬儀 ...
- ◇第06位:3万円お位牌魂入れ・開眼供養:宗派指定5千円追加!
- ◇第07位:位牌の魂入れ(性根入れ)のお布施相場をお寺に聞いてみました
- ◇第08位:位牌・魂入れ・開眼供養とは(白木位牌・本位牌・開眼供養法要・法名軸 ...
- ◇第09位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第10位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- グーグルで「魂入れ 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第02位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第03位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第04位:浄土真宗 大谷派の仏像・位牌・仏壇について
- ◇第05位:4万円「白木位牌魂抜き+本位牌魂入れ」セットの割引料金!
- ◇第06位:戒名(法名・法号)授与のみ
- ◇第07位:3万円お位牌魂入れ・開眼供養:宗派指定5千円追加!
- ◇第08位:お仏壇開き、開眼供養(かいげん)魂入れ、入魂式
- ◇第09位:天台宗・西巌殿寺
- ◇第10位:イオン×はせがわオンラインショップ / 位牌と戒名
- グーグルで「魂入れとは」と検索してみました。
- ◇第01位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第02位:仏壇の魂入れとは?|お布施・金額相場・準備・流れ・服装|終活ねっと
- ◇第03位:仏壇を買った後は開眼供養が必要!|開眼供養の準備と流れ
- ◇第04位:お墓の「魂入れ」って何?|開眼供養・お供え物・お布施・マナー|終活 ...
- ◇第05位:開眼供養・開眼法要とは – 日程と当日の流れ/お墓・仏壇・魂入れ・納骨 ...
- ◇第06位:名言、故事成語に学ぶ人材マネジメントの本質 - 第5回「仏作って魂入れ ...
- ◇第07位:仏壇を購入したい!購入するべき時期、購入のポイントについて解説 | お ...
- ◇第08位:【お気持ちっていくら?】お仏壇の引っ越し方法!魂抜きとお布施の相場 ...
- ◇第09位:「仏作って魂入れず」の英語・英語例文・英語表現 - Weblio和英辞書
- ◇第10位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- グーグルで「魂入れ 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:お墓の「魂入れ」って何?|開眼供養・お供え物・お布施・マナー|終活 ...
- ◇第02位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第03位:仏作って魂入れず - Magic Hour Blog
- ◇第04位:「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」放送内容 TBSテレビ:世界 ...
- ◇第05位:トルコ、中期経済計画は「仏作って魂入れず」か? | 第一生命経済研究所 ...
- ◇第06位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第07位:開眼供養・開眼法要とは – 日程と当日の流れ/お墓・仏壇・魂入れ・納骨 ...
- ◇第08位:「白木位牌」から「本位牌」へ。いつまでに必要?どのようにして作る ...
- ◇第09位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第10位:GHQでなく日本人が魂入れた憲法25条・生存権 (2ページ目):日経 ...
- グーグルで「魂入れ 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第02位:「白木位牌」から「本位牌」へ。いつまでに必要?どのようにして作る ...
- ◇第03位:墓誌の意味とは – 戒名彫刻、その費用(墓誌の価格、名入れ、追加彫刻 ...
- ◇第04位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第05位:位牌の魂入れなどの情報についてまとめてみました|終活ねっと
- ◇第06位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第07位:位牌の魂入れ(性根入れ)のお布施相場をお寺に聞いてみました
- ◇第08位:開眼供養・開眼法要とは?行う時期・服装・必要な費用など
- ◇第09位:位牌の安置場所・位牌の魂入れ
- ◇第10位:夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること|葬儀 ...
- グーグルで「魂入れ 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:Q & A|浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺
- ◇第02位:浄土真宗に位牌は必要ない?|浄土真宗の位牌の考え方
- ◇第03位:墓誌の意味とは – 戒名彫刻、その費用(墓誌の価格、名入れ、追加彫刻 ...
- ◇第04位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第05位:夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること|葬儀 ...
- ◇第06位:3万円お位牌魂入れ・開眼供養:宗派指定5千円追加!
- ◇第07位:位牌の魂入れ(性根入れ)のお布施相場をお寺に聞いてみました
- ◇第08位:位牌・魂入れ・開眼供養とは(白木位牌・本位牌・開眼供養法要・法名軸 ...
- ◇第09位:魂入れ(開眼法要・お性根入れ)とは | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第10位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- グーグルで「魂入れ 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:涙そうそうは、お位牌関連サービス・商品をトータルに値ごろ価格で提供!
- ◇第02位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第03位:お寺さんへお位牌を送って、魂入れ・開眼供養が1万円で出来ます!
- ◇第04位:浄土真宗 大谷派の仏像・位牌・仏壇について
- ◇第05位:4万円「白木位牌魂抜き+本位牌魂入れ」セットの割引料金!
- ◇第06位:戒名(法名・法号)授与のみ
- ◇第07位:3万円お位牌魂入れ・開眼供養:宗派指定5千円追加!
- ◇第08位:お仏壇開き、開眼供養(かいげん)魂入れ、入魂式
- ◇第09位:天台宗・西巌殿寺
- ◇第10位:イオン×はせがわオンラインショップ / 位牌と戒名
- グーグルで「納骨供養とは」と検索してみました。
- ◇第01位:開眼供養・開眼法要とは – 日程と当日の流れ/お墓・仏壇・魂入れ・納骨 ...
- ◇第02位:納骨にかかる費用は?さまざまな納骨方法から比較・検索ができる ...
- ◇第03位:納骨の時期や方法、費用、手順や準備するもの/参列者や遺族のマナー ...
- ◇第04位:納骨・永代供養・塔婆
- ◇第05位:一心寺 納骨とお骨佛
- ◇第06位:納骨式の服装は喪服でなくても良い!時期に合わせた服装について解説 ...
- ◇第07位:【解説】納骨堂と永代供養墓の違いは?納骨堂での供養の費用相場は ...
- ◇第08位:永平寺の法要のご案内(納骨・供養)
- ◇第09位:永代供養と納骨堂の違いは?メリット・デメリットと相場で比較 | お墓探し ...
- ◇第10位:AEON 納骨・永代供養墓はイオンライフにお任せください
- グーグルで「納骨供養 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:2万円~永代供養の送骨(委託)納骨なら「安心宣言」の涙そうそう!
- ◇第02位:さいたま市の永代供養 納骨堂- 東光寺 おおみや涅槃堂 | 供養の内容
- ◇第03位:2万円~!経済性追求の合祀タイプ納骨堂しか取り扱っていません!
- ◇第04位:永代供養 | 永代供養|龍泉寺
- ◇第05位:ペット葬儀、火葬、納骨、供養なら道南ペット霊園函館
- ◇第06位:供養形態ー納骨堂
- ◇第07位:納骨について | お寺のペット霊園 沙羅の苑(さらのその)
- ◇第08位:福岡の永代供養・樹木葬・納骨堂・お墓を探すなら|アノヨコノヨ
- ◇第09位:永代供養墓について | 佼成霊園
- ◇第10位:永代供養とは? 永代使用との違いってなに?|お墓について|お墓の ...
- グーグルで「納骨供養 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:一心寺 納骨とお骨佛
- ◇第02位:戒名って永代供養墓にも必要?戒名不要の選択肢がある?|終活ねっと ...
- ◇第03位:法要・供養 | 千葉の納骨堂・生前戒名 萬徳院 釈迦寺
- ◇第04位:お布施の相場は? 戒名によって金額は違う? 渡し方やタイミングも紹介 ...
- ◇第05位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第06位:水子供養・赤ちゃん供養、お位牌や戒名、お骨壷・仏壇について
- ◇第07位:永代供養ー埼玉県飯能市の納骨堂-入間市・狭山市・日高市 | 真言宗智山 ...
- ◇第08位:死産の赤ちゃんの供養や、葬儀、火葬の方法について|葬儀・葬式なら ...
- ◇第09位:曹洞宗系・真光寺 - 永代供養ネット
- ◇第10位:お問い合わせ | 高野山真言宗 総本山金剛峯寺
- グーグルで「納骨供養 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:永代供養|実成寺/實成寺
- ◇第02位:一心寺 納骨とお骨佛
- ◇第03位:永代供養・納骨堂を愛知県名古屋でお探しなら
- ◇第04位:戒名と法名と院号はどう違うの? | 永代供養・納骨の浄土真宗光乗寺
- ◇第05位:浄土真宗(西)・光乗寺(こうじょうじ) - 永代供養ネット
- ◇第06位:永代供養のご案内 - 和宗総本山 四天王寺
- ◇第07位:永代供養納骨堂/一時納骨 神奈川県横浜市の聖徳しらはた淨苑
- ◇第08位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第09位:つけなければいけないもの?戒名の必要性について考える
- ◇第10位:安心で格安な永代供養墓2万円~、全国120カ寺以上から選べます!
- グーグルで「納骨供養 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:日蓮宗・妙福寺 - 永代供養ネット
- ◇第02位:戒名・法名・法号授与2万円~なら安心宣言の涙そうそう(終楽)!
- ◇第03位:日蓮宗・妙行寺安穏墓苑 - 永代供養ネット
- ◇第04位:戒名(法名・法号)授与のみ
- ◇第05位:永代供養墓へのご遺骨運搬方法と納骨費用(料金)2万円~
- ◇第06位:戒名料は2~100万円?戒名の相場とランクを選ぶ基準|小さなお葬式 ...
- ◇第07位:戒名・法名・法号に。各宗派の寺院住職様が戒名を授与
- ◇第08位:永代納骨供養墓
- ◇第09位:終活サポート。納骨やお墓購入も対応しています。
- ◇第10位:佼成霊園について | 佼成霊園
- グーグルで「水子供養とは」と検索してみました。
- ◇第01位:水子供養とは?お布施の金額や自宅で行うときの方法|葬儀・葬式なら ...
- ◇第02位:水子供養はどんな風にすべき?方法や流れって?
- ◇第03位:水子供養とは【千葉厄除け不動尊】
- ◇第04位:水子供養|京都東福寺霊源院
- ◇第05位:水子供養の正しい方法は?流産・中絶では行うべき?|流れ・費用|終 ...
- ◇第06位:水子供養とは何をするの?方法・依頼先・費用相場を解説 | お墓さがし
- ◇第07位:水子 - Wikipedia
- ◇第08位:水子供養Q&A
- ◇第09位:先祖供養・水子供養|大本山 中山寺|ご冥福をお祈りしてご供養いたし ...
- ◇第10位:水子供養ナビ
- グーグルで「水子供養 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:水子供養とは?お布施の金額や自宅で行うときの方法|葬儀・葬式なら ...
- ◇第02位:水子供養はどんな風にすべき?方法や流れって?
- ◇第03位:水子供養Q&A
- ◇第04位:水子供養とは【千葉厄除け不動尊】
- ◇第05位:水子供養|京都東福寺霊源院
- ◇第06位:水子供養・ペット葬・祈願
- ◇第07位:水子供養ナビ
- ◇第08位:水子供養
- ◇第09位:水子地蔵のお参りの仕方を解説!
- ◇第10位:水子供養Q&A
- グーグルで「水子供養 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:水子供養・赤ちゃん供養、お位牌や戒名、お骨壷・仏壇について
- ◇第02位:水子供養はどんな風にすべき?方法や流れって?
- ◇第03位:水子供養と位牌 | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第04位:水子供養Q&A
- ◇第05位:水子供養とは?お布施の金額や自宅で行うときの方法|葬儀・葬式なら ...
- ◇第06位:命日とは・戒名とは『関東水子供養霊場 千葉子安地蔵尊』
- ◇第07位:水子供養・ペット葬・祈願
- ◇第08位:水子についてQ&A | 寶珠山 大観音寺
- ◇第09位:水子供養(来寺供養)【浄土宗感応寺】東京都世田谷区
- ◇第10位:水子供養 高野山真言宗 出雲厄除け大師 倉留寺
- グーグルで「水子供養 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:水子供養はどんな風にすべき?方法や流れって?
- ◇第02位:先祖供養・水子供養|大本山 中山寺|ご冥福をお祈りしてご供養いたし ...
- ◇第03位:水子供養Q&A
- ◇第04位:水子供養・赤ちゃん供養、お位牌や戒名、お骨壷・仏壇について
- ◇第05位:水子供養と位牌 | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第06位:水子供養とは?お布施の金額や自宅で行うときの方法|葬儀・葬式なら ...
- ◇第07位:永代供養のご案内 - 和宗総本山 四天王寺
- ◇第08位:法名碑 法名軸 本位牌 水子位牌 手元供養 夫婦位牌 彫刻 ペット用位牌 ...
- ◇第09位:位牌 モダン位牌 6点セット 水子供養 49日法要 クリスタル 手元供養 仏具 ...
- ◇第10位:法事・御祈祷・霊断・葬儀等 - 境内散策 | 青森の日蓮宗廣布山蓮華寺
- グーグルで「水子供養 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:水子供養はどんな風にすべき?方法や流れって?
- ◇第02位:水子供養・赤ちゃん供養、お位牌や戒名、お骨壷・仏壇について
- ◇第03位:水子供養と位牌 | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第04位:3万円水子供養:僧侶派遣(お坊さん手配)なら涙そうそう!
- ◇第05位:水子供養とは?お布施の金額や自宅で行うときの方法|葬儀・葬式なら ...
- ◇第06位:先祖を祀る|お供養 【納骨・永代供養・永代水子供養・先祖供養】 監修 ...
- ◇第07位:水子供養について
- ◇第08位:水子供養Q&A
- ◇第09位:葬儀案内 | 實秀山 安養寺
- ◇第10位:水子供養Q&A
- グーグルで「祥月命日とは」と検索してみました。
- ◇第01位:月命日とは?命日の意味と月命日のお供えマナー
- ◇第02位:『祥月命日』と『月命日』のちがいとは? – ニッポン放送 NEWS ONLINE
- ◇第03位:祥月命日にすること | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第04位:祥月命日
- ◇第05位:祥月命日
- ◇第06位:祥月とはなんですか?祥月の意味 | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第07位:命日 - Wikipedia
- ◇第08位:祥月命日(しょうつきめいにち)の意味や読み方 Weblio辞書
- ◇第09位:別所公祥月命日法要 - 三木市ホームページ
- ◇第10位:「祥月命日」の英語・英語例文・英語表現 - Weblio和英辞書
- グーグルで「祥月命日 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:『祥月命日』と『月命日』のちがいとは? – ニッポン放送 NEWS ONLINE
- ◇第02位:祥月命日
- ◇第03位:祥月命日にすること | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第04位:月命日とは?命日の意味と月命日のお供えマナー
- ◇第05位:別所公祥月命日法要 - 三木市ホームページ
- ◇第06位:命日の過ごし方はどうすればよい? 供養の方法は?|株式会社加登
- ◇第07位:祥月命日
- ◇第08位:祥月命日(しょうつきめいにち)の意味や読み方 Weblio辞書
- ◇第09位:「祥月命日」の英語・英語例文・英語表現 - Weblio和英辞書
- ◇第10位:命日 - Wikipedia
- グーグルで「祥月命日 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:永代祠堂 - ご先祖供養・ご納骨|浄土宗総本山 知恩院
- ◇第02位:法事の前倒しは?
- ◇第03位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第04位:永代供養の善勝寺|永代供養合同墓 東光山合同船納骨規定
- ◇第05位:位牌彫刻について
- ◇第06位:永代供養墓について | 佼成霊園
- ◇第07位:お経の出るお線香。灰に文字、お題目、戒名。
- ◇第08位:永代供養のご案内 | 世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺
- ◇第09位:名古屋 先祖供養|供養・祈祷のご案内|八事山興正寺
- ◇第10位:お布施の目安早見表 | 大人のためのbetterlife マガジン『enpark』
- グーグルで「祥月命日 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:法名軸 - Wikipedia
- ◇第02位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第03位:法要案内に年忌該当だけでなく祥月命日もご案内するには? | 沙羅.com
- ◇第04位:永代経をあげる ※2019年10月から受付方法が変わりました。|参拝 ...
- ◇第05位:法名軸作成について - 仏壇仏具・いっぴん堂 - 通販 - Yahoo!ショッピング
- ◇第06位:高麗陣打死衆供養石碑 - 南あわじ市ホームページ
- ◇第07位:沙羅
- ◇第08位:過去帳の書き方 | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第09位:納骨らいはい所・平和公園墓地
- ◇第10位:年忌表
- グーグルで「祥月命日 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:法名軸 - Wikipedia
- ◇第02位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第03位:過去帳 - Wikipedia
- ◇第04位:(2ページ目)浄土真宗大谷派の教えとは?|歴史・お仏壇・おつとめ・お墓 ...
- ◇第05位:過去帳の書き方 | 仏壇・仏具のことなら「いい仏壇」
- ◇第06位:仏縁堂ブランド:国産仏具【金襴鳥の子上製過去帳:上金紺3.5 ... - Amazon
- ◇第07位:沙羅
- ◇第08位:お経の出るお線香。灰に文字、お題目、戒名。
- ◇第09位:法事・法要の基礎知識|いい葬儀
- ◇第10位:ご供養とご供養料|共生(ともいき)
- グーグルで「お盆とは」と検索してみました。
- ◇第01位:お盆 - Wikipedia
- ◇第02位:お盆とはなんですか?お盆の意味 | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第03位:お盆とは|地域によって期間の違い
- ◇第04位:知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!
- ◇第05位:お盆とは – 時期とやること、過ごし方、意外と知らない成り立ちと作法 ...
- ◇第06位:お盆の時期はいつ?新盆(7月盆)と旧盆(8月盆)の地域と違い
- ◇第07位:お盆の常識~仏事まめ百科|メモリアルアートの大野屋
- ◇第08位:お盆とは | <公式サイト>APIOアピオ|株式会社ファミリーラブ
- ◇第09位:お盆の話
- ◇第10位:2019年のお盆はいつ?期間・由来・過ごし方や準備・お供え物を解説 ...
- グーグルで「お盆 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:お盆期間中の営業内容について < お知らせ 絹島温泉ベッセルおおちの湯
- ◇第02位:知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!
- ◇第03位:盆・お盆】お盆とは・盆飾り・いつ・期間・お盆の入り/墓参り/供養/送り火
- ◇第04位:おきなわ新喜劇 - \ 今年は沖縄のお盆を学べる内容です / 第6回おきなわ ...
- ◇第05位:【夏季(お盆)休診日のお知らせ】 | 診療内容 | 休日診療|ほつか ...
- ◇第06位:ワクワクピカピカお盆のフェア【イベント内容中止・変更のお知らせ】|tys ...
- ◇第07位:お盆限定『みなみな屋お盆キャンペーン』 | 南三陸町観光協会公式HP
- ◇第08位:お盆期間(8/12~19)の食事内容変更のお知らせ | 下風呂観光ホテル ...
- ◇第09位:お盆の時期はいつ?盆飾りとお供え、新盆、盆提灯、香典の目安などお盆 ...
- ◇第10位:第6回おきなわ新喜劇ツアー「オジー オズ お盆〜ん!」
- グーグルで「お盆 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:お盆の法要で気をつけるべきことは?法要の常識とマナーまとめ
- ◇第02位:【楽天市場】【盆提灯・盆ちょうちん】家紋・戒名入 お盆提灯 回転行灯 ...
- ◇第03位:初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ
- ◇第04位:家紋・戒名入 お盆提灯 回転行灯 立花桜調8号 3952-1N-2 一対セット(2 ...
- ◇第05位:お盆のおはなし | 千葉の納骨堂・生前戒名 萬徳院 釈迦寺
- ◇第06位:盆提灯の種類は?大内提灯・戒名入り・家紋入り・御霊前・など豊富に ...
- ◇第07位:お盆提灯(盆ちょうちん)がよくわかる
- ◇第08位:家紋・戒名入り 盆提灯 盆ちょうちん お盆提灯 あけぼの LED コードレス ...
- ◇第09位:棚経とはなんですか?棚経の意味 | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- ◇第10位:新盆に飾る白提灯ってどんなもの?飾り方や処分方法を解説します ...
- グーグルで「お盆 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:別院のお盆|法要行事|お参りする|お東ネット 東別院
- ◇第02位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第03位:墓誌 墓標 法名碑 霊標 お墓参り お盆 お彼岸 :yks03990001:横田石材 ...
- ◇第04位:【楽天市場】墓誌 墓標 法名碑 霊標お墓参り お盆 お彼岸 送料無料:横田 ...
- ◇第05位:浄土真宗(西)・光乗寺(こうじょうじ)
- ◇第06位:【楽天市場】仏像・掛軸・ご本尊 > 掛軸(ご本尊・脇掛) > 掛軸 法名軸(浄土 ...
- ◇第07位:浄土真宗(西)・光乗寺(こうじょうじ)
- ◇第08位:【楽天市場】盆提灯 霊前灯 【 和照灯 戒名・法名入 】 コードレス (No ...
- ◇第09位:家紋入行灯|盆提灯|お仏壇のはせがわ お盆提灯特設サイト
- ◇第10位:【楽天市場】仏具 『過去帳 錦金蘭 4寸』[お仏壇用][帳面] (過去帳 戒名 ...
- グーグルで「お盆 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:法事に関するキーワード一覧|終活ねっとのお坊さん
- ◇第02位:彼岸供養の読経料
- ◇第03位:法号の意味とは?法号とは何か、解説いたします|終活ねっとのお坊さん
- ◇第04位:【楽天市場】【盆提灯・盆ちょうちん】家紋・戒名入 お盆提灯 回転行灯 ...
- ◇第05位:曹洞宗・東長寺(トウチョウジ)
- ◇第06位:善應院|妙法の郷
- ◇第07位:日蓮宗・妙行寺安穏墓苑
- ◇第08位:盆提灯の選び方|なごみ工房
- ◇第09位:その他|近くのお墓
- ◇第10位:のし袋の表書き
- グーグルで「お彼岸とは」と検索してみました。
- ◇第01位:お彼岸とはどういう意味?由来やお盆との違いを解説
- ◇第02位:春のお彼岸・秋のお彼岸
- ◇第03位:2020年(令和2年)春秋のお彼岸、期間はいつからいつまで?|株式会社 ...
- ◇第04位:お彼岸(ひがん) ってなぁに?・なぜなに特集 こんごういんキッズ
- ◇第05位:お彼岸の意味や、過ごし方について教えてください【Q&A】 | 霊園・墓地の ...
- ◇第06位:彼岸 - Wikipedia
- ◇第07位:お彼岸って何ですか?|仏事の知識と心得|仏事ここが知りたい ...
- ◇第08位:お彼岸について
- ◇第09位:【秋彼岸】2019年秋彼岸の日程は?お彼岸の意味~お布施の目安まで ...
- ◇第10位:お彼岸のお供え物は?春・秋のお彼岸の迎え方・準備について
- グーグルで「お彼岸 内容」と検索してみました。
- ◇第01位:お彼岸はいつ?準備や行事の内容|2018年の春と秋のお彼岸 | 法事 ...
- ◇第02位:お彼岸って何ですか?|仏事の知識と心得|仏事ここが知りたい ...
- ◇第03位:お彼岸とはどういう意味?由来やお盆との違いを解説
- ◇第04位:お彼岸イベント開催! | お知らせ | 農産物直売所 | 株式会社JA松本市 ...
- ◇第05位:お彼岸(ひがん) ってなぁに?・なぜなに特集 こんごういんキッズ
- ◇第06位:春のお彼岸手土産準備特集 - イオンモール太田公式ホームページ
- ◇第07位:彼岸 - Wikipedia
- ◇第08位:初彼岸とお返しマナー/香典返し・法事のお返し・49日引き出物専門店 ...
- ◇第09位:お彼岸とは?意味や言葉の由来、過ごし方について解説します|小さなお ...
- ◇第10位:【お彼岸こそ、手紙参り】手紙参り体験会 毎回内容が変わってくる編 ...
- グーグルで「お彼岸 戒名」と検索してみました。
- ◇第01位:お彼岸に必要な基礎知識!基本とマナーを押さえよう
- ◇第02位:卒塔婆・塔婆とはなんですか?卒塔婆・塔婆の意味 | 大人のための ...
- ◇第03位:今さら聞けないお彼岸のマナー!お墓参りに必要な知識まとめ
- ◇第04位:【楽天市場】戒名文字入れ・機械彫り(一戒名分)【お盆用品 仏具 お彼岸 ...
- ◇第05位:お彼岸とはどういう意味?由来やお盆との違いを解説
- ◇第06位:供養・祈祷のご案内 - 参拝・供養・祈祷 - 和宗総本山 四天王寺
- ◇第07位:【楽天市場】寺院仏具・密教法具 > 華皿・散華・戒名紙:仏壇 盆提灯 数珠 ...
- ◇第08位:お彼岸セール「つや姫」1袋付 すとうのお位牌 彫刻又は書き戒名 一霊位 ...
- ◇第09位:神道に戒名は無い?諡(おくりな)とは|小さなお葬式のコラム
- ◇第10位:お彼岸セール「つや姫」1袋付 すとうのお位牌 彫刻又は書き戒名一霊位付 ...
- グーグルで「お彼岸 法名」と検索してみました。
- ◇第01位:墓誌 墓標 法名碑 霊標 お墓参り お盆 お彼岸 :yks03990001:横田石材 ...
- ◇第02位:春のお彼岸|別院のお彼岸(春、秋)|法要行事|お参りする|お東ネット ...
- ◇第03位:浄土真宗の場合お布施はいくら包む?お布施の包み方や渡し方もご紹介 ...
- ◇第04位:縦25.3cm×横6.5cm【寺院仏具 お彼岸】
- ◇第05位:戒名の現れるお線香 法名の出る線香花の香り「現字浄心香 戒名 法名他」
- ◇第06位:【楽天市場】墓誌 墓標 法名碑 霊標お墓参り お盆 お彼岸 送料無料:横田 ...
- ◇第07位:お彼岸とはどういう意味?由来やお盆との違いを解説
- ◇第08位:卒塔婆・塔婆とはなんですか?卒塔婆・塔婆の意味 | 大人のための ...
- ◇第09位:お彼岸に必要な基礎知識!基本とマナーを押さえよう
- ◇第10位:法名とはなんですか?法名の意味 | 大人のためのbetterlife マガジン ...
- グーグルで「お彼岸 法号」と検索してみました。
- ◇第01位:【楽天市場】【寺院用仏具】法号包紙(戒名包紙) 小型(50枚綴) 縦26cm ...
- ◇第02位:日蓮宗・一妙寺
- ◇第03位:戒名|いい葬儀
- ◇第04位:彼岸供養の読経料 - 法事法要「お坊さん.jp」
- ◇第05位:樹林墓地「そせい」お申し込み・お問い合わせ・資料請求|本行寺
- ◇第06位:法事・法要へのお坊さんのご手配なら「法事法要サポート」 | 法要関連 ...
- ◇第07位:お位牌の種類や選び方、戒名の知識ご紹介。
- ◇第08位:名古屋の墓石なら華石へ|戒名彫りとは
- ◇第09位:2016
- ◇第10位:法要お申込フォーム
- グーグルで「初七日とは」と検索してみました。
お支払いについて
お坊さん手配・派遣・出張、永代供養、墓じまい、仏壇じまい®などのお支払いは、口座かクレジットカード決済、電子マネー(AmazonPay・LinePay)による前払い方式です。お葬式のみ、葬儀終了後の葬儀社さんへ現金支払いとなります。
取引先さん募集
■終楽は、取引先さんとの共存共栄を目指します!
■取引先さんと終楽(涙そうそう)は、対等の立場で相互の信頼関係構築を目指します!
■取引先さんと終楽(涙そうそう)の役割、取引先さんの施工と涙そうそう(終楽)のお客様斡旋・売上回収を相互理解し、お客様志向(ファースト)に徹します。
お問合せ・お申込み先
■戒名授与:050-5578-3842
■全国対応・年中無休・受付時間
■時間外はメールにてお問い合わせ下さい
戒名・法名・法号授与の目次

【平日/土日祝】9:00~17:00

【土日祝はお電話が繋がりにくいためメールでのお問合せを推奨いたします】
※フリーダイヤルではありません。料金が気になる方は「折り返し希望」とお伝えください。




















